ISO19475とは?概要や規格制定の背景、活用例を解説

企業がDXを推進するためには、さまざまな取り組みが必要です。DXの目的は、ビジネスモデルの変革ですが、それを引き起こすためには企業が抱えている現状の課題を分析できるように大量のデータが必要になります。そして、分析にはアナログの情報をデジタル化することが求められるため、文書を電子化することは必須です。
しかし、文書をデジタル化して流通させる場合、『文書の信頼性』という課題が生じます。その文書が本物なのかを見分ける必要があるため、信頼性を担保するためにISO19475という国内外の規格が制定されています。
DXの推進や文書のデジタル化を推進する際、ISO19475は頻繁に登場する規格となるため、知識として把握しておくと便利です。
今回は、ISO19475の概要や規格制定の背景、活用事例などについて詳しく解説しますので、興味がある方は、ぜひチェックしてください。
目次 [非表示]
ISO19475とは?概要を具体的に解説

ISO19475とは、企業や組織の文書情報の取り扱いを定めた文書マネジメントを統合運用するための規格です。日本文書マネジメント協会、通称JIIMAがデジタルトランスフォーメーションを支えていくため、電子化文書を安全に取り扱うことができるように開発された規格となります。
2017年2月にDIS投票が開始されてこの投票によって各国の承認が得られたため、2017年末から国際標準として発行されました。ISO19475が発行されたことによって業務で発生するリスクの軽減や業務活動の効率化及び活発化を期待することができるため、より安全なデジタル社会の実現に貢献しています。
文書の取り扱い規格制定の背景
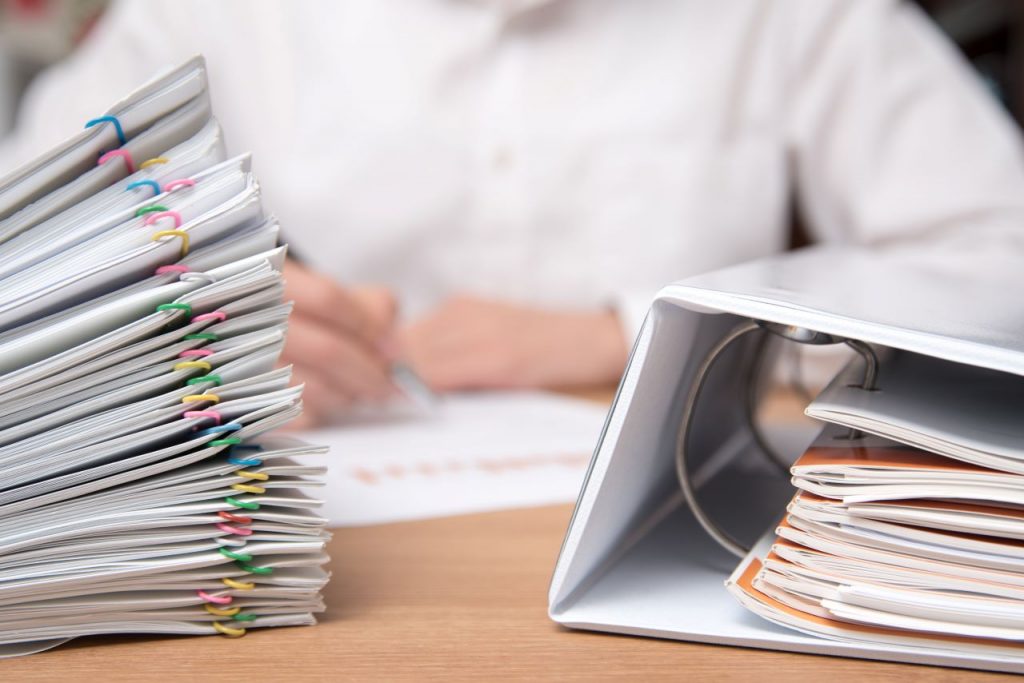
文書の取り扱い規格制定の背景は以下の3つです。なぜ、ISO19475が必要なのかがわかるので、ぜひ参考にしてください。
欧米より10年あまり遅れをとっているデジタル化
日本は、先進国の中でもデジタル化が遅れているといわれています。実際に、それを実感する機会は非常に多いです。例えば、行政の手続きは、直接行政機関に足を運ぶ必要があります。また、運転免許証やマイナンバーなどの公的証明書は、警察署や運転免許センター、市役所などに直接受け取りに行かなければなりません。さらに、企業などでも後述するように許可を得るためには上司の署名・捺印が必要だったり、重要な書類を紙で管理していたりするケースも多いです。
一方、デジタル社会が広く浸透している欧米諸国では、文書の電子化が進んでおり、その信頼性においても証拠となる文書の取り扱い規則や電子証拠と判定するための規則を設けることで担保されています。
日本では、文書の一部を電子化して作業の結果を保存することを認めたe-文書法が制定されています。しかし、電子化した文書の取り扱いにおいては欧米よりも整備が乏しく、約10年以上遅れをとっているといわれているのです。そのため、電子化文書を安全に取り扱うためや業務効率を促進するために、文書の信頼性を担保する規格が必要となりました。
ハンコレスによる文書の安全性確保が困難な状況
2020年、世界的に新型コロナウイルスが流行しました。日本でも2020年1月16日に国内で感染者が確認され、その後、日本各地で感染が確認されるようになりました。
新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため、政府が企業にテレワーク7割を推進し、日本でも自宅から仕事をするという働き方が珍しいものではなくなりました。企業がテレワークを推進するにあたり直面する課題は数多くありますが、その中にひとつに紙による情報共有ができなくなったことが挙げられます。従業員が自宅から仕事をする場合、紙で情報共有を行おうとすると手段は郵送となってしまいます。非常に効率が悪く、情報共有に時間が必要です。そのため、ペーパレス化やハンコレス化で業務再構築を余儀なくさせられた企業は増えました。
しかし、文書の信頼性を担保するためには、ハンコを使わなければならない企業もいます。例えば、ハンコがあるからその文書が原本であると判断できますし、上司から承認を得ている契約書であることがわかります。そのため、現在でもハンコや紙を使用していたり、ハンコの代わりに運転免許書の写しを要求されたりするケースは珍しくありません。このように、電子化文書では文書の信頼性を担保することが難しく、今でも紙やハンコが主流になっている企業も存在します。
電子化文書の安全性を確保するための施策が必要
原本は、内容の改ざんやコピーを防止するために、特殊な複写防止用紙が使用されていたり、割印などを押していたりするケースが多いです。しかし、電子化文書は常に更新や複製が可能になります。このことが日本でデジタル社会推進のハードルを高めていた理由のひとつです。
ISO19475の3つの活用例

ISO19475は、ペーパレス及びハンコレスで文書の信頼性を担保することができる最低限の規格となります。しかし、どのような場面で実際に活用されているのか把握しておきたいという方もいるのではないでしょうか?ここでは、ISO19475の活用例を3つご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
電子インボイス制度における安全性の確保
1つ目は、電子インボイス制度における安全性の確保です。
電子インボイスは2023年10月1日から導入されるインボイス制度で仕入れ額控除の適用を受けるために必要な適格請求書を電子化した請求書のことです。ISO19475によって文書の取り扱いに対して安全性を確保した組織間流通の証明を行うことができます。
データ納品された情報の権利や品質の保持
2つ目は、データ納品された情報の権利や品質の保持です。
不適切な流通ルートから受領した文書の安全性を担保することができるため、納品データの情報の権利や品質を保持することが可能です。これにより文書の安全性が担保されます。
業務委託関連文書の指示時の権利保持
3つ目は、業務委託関連文書の指示時の権利保持です。
業務委託契約を締結した委託先にデータを提示したり、仕様書を提示したりするとき、内容の安全性を証明する必要があります。この際もISO19475が活用されます。
電子化文書を安全に取り扱うためには?

電子化文書は原本よりも複製や編集がしやすくなるため、その分安全性には十分に配慮することが求められます。具体的に、どのように電子化文書を安全に取り扱えばいいのかについて解説しますので、ペーパレス化等を推進したい企業はチェックしてみてください。
はじめに文書をスキャンして電子化をする
ペーパレス・ハンコレスを実現するためには、まず原本をスキャンして文書を電子化する必要があります。例えば、ISO19475では電子帳簿保存法のスキャナ保存においても保存したあと検索がしやすいように検索用の台帳の作成や改ざんを抑制するためにタイムスタンプの付与などを規定していますが、そもそも文書が電子化されていない場合、ISO19475の規定に沿った運用が難しくなります。
企業の中には、スキャンするべき文書が多く、自社のみで対応できないというところは少なくありません。そのような企業は、素早く大量の文書をスキャンしてくれる代行業者を利用するのがおすすめです。
要件に沿って社内ルールを決めていく
文書をスキャンすることも非常に重要な取り組みになりますが、それ以上に要件に沿って社内ルールを決めていくことが大切です。
実際に、欧米諸国では文書取り扱いの安全性を確保するために、『文書を安全に生成し、受信する手順を組織でルール化する』や『文書を安全に送付する場合にマーキングを管理・コントロールする』など社内ルールの構築やそれに従うことに重点を置いています。そのため、スキャンをすることも重要ですが、要件に沿って社内ルールを決めることで、電子化文書を安全に取り扱うことができる体制を構築することができるでしょう。
まとめ
今回は、ISO19475の概要や必要とされる背景などについて詳しく解説しました。ISO19475は電子化文書の信頼性を担保し安全に取り扱うために制定された規格です。DXの推進などさまざまな場面で活用されますので、この機会に覚えておくのがおすすめです。また、電子化文書を社内で運用するためには、はじめにスキャンが必要です。企業の中には、これからペーパレス化を推進するために、スキャンを検討している方もいるのではないでしょうか?
DX推進のための文書電子化を行いたいという企業は、株式会社うるるの『うるるBPOスキャン代行サービス』を利用してみませんか?うるるBPOスキャン代行サービスは短納期で大量の文書をスキャンしてくれる専門業者です。そのため、素早くDX推進に取り組みたい企業は手厚いサポートを受けることができます。興味がある方は、下記のリンクからお気軽にご相談ください。
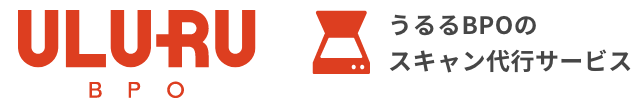
 0120-269-356
0120-269-356